「心地良い人間関係は、距離感で決まる」と言い切れるくらい、距離感は大事です。
でも、うまく距離感を取れない(取ってくれない)人に出くわすことがあります。
例えば、急に距離を詰めてくる人。かと思えば、急に離れていく人。このような人の対応に困ったり、モヤモヤすることはありませんか?
今回は距離を急速に詰めてきては急速に離れる。こんな「付き合いにくい人」についてお伝えします。
人間関係のストレスが、少しでも減ることを願っています。
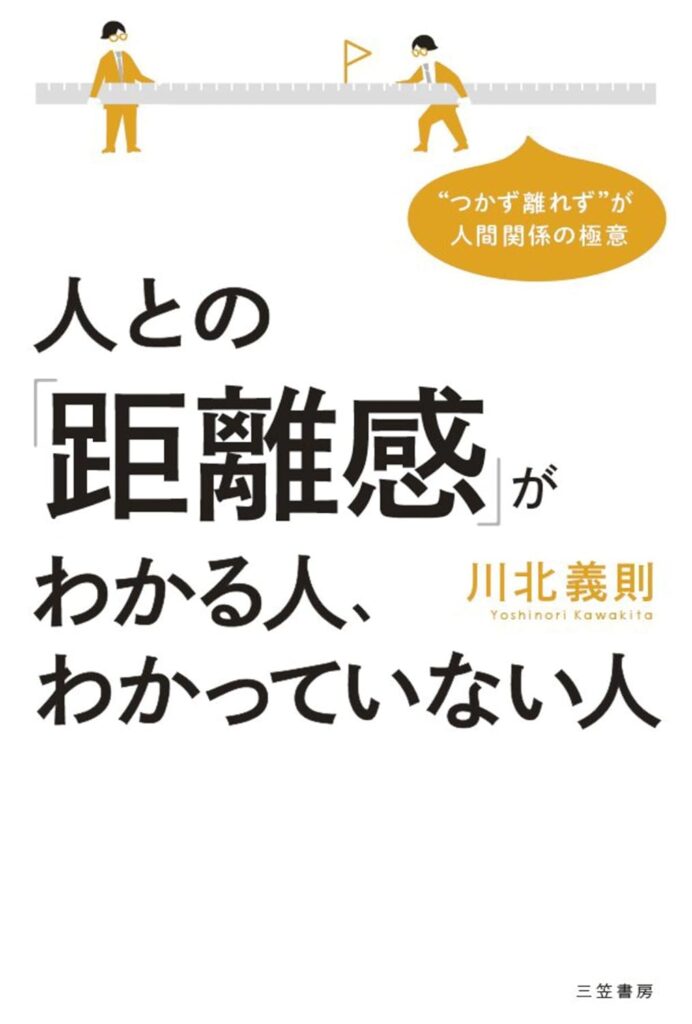
距離感を急に詰めてくる人は隠れ承認欲求をもっている
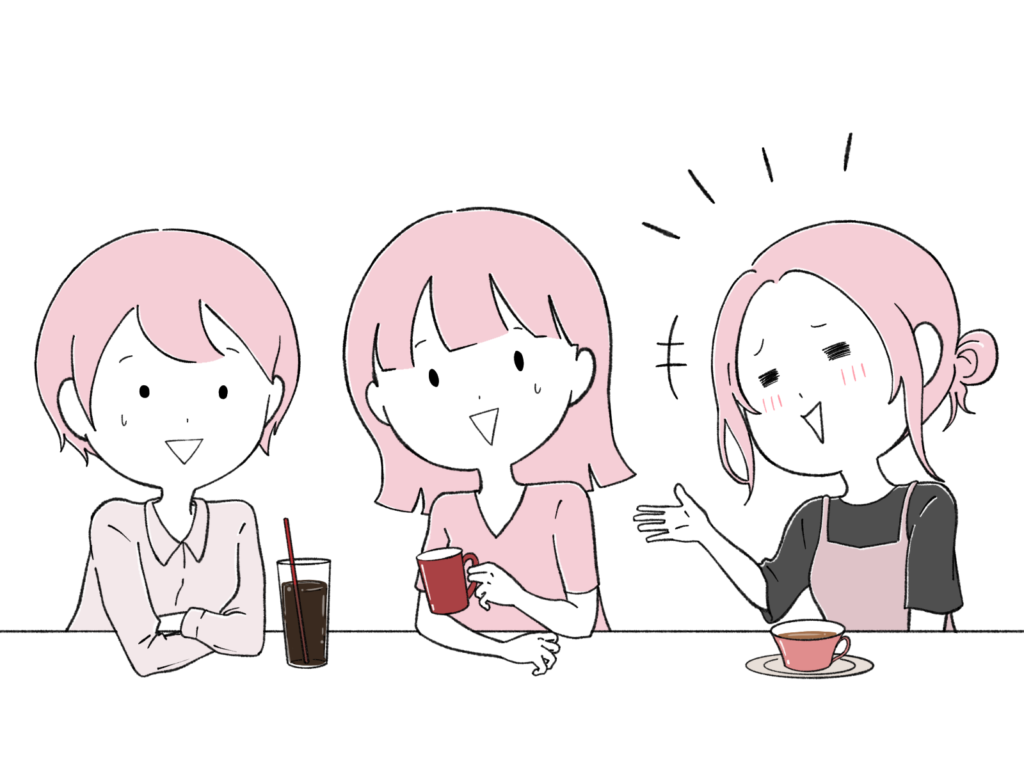
距離感を急に詰めてくる人は、「隠れ承認欲求」を持っています。
承認欲求は、大なり小なり誰しも持っているものですが、強すぎると生きづらくなってしまいます。
承認欲求とは、「他人から一目置かれたい」「自分を認めてほしい」という欲求です。ネガティブな意味で使われることもありますが、承認欲求を満たすことは人間の自然な欲求の1つでもあります。
しかし、あまりにも承認欲求が高すぎると、普段の生活にも良くない影響が生じます。例えば、上司に認めてもらえないことに落ち込んでしまったり、小さなことをいつまでも気にしてしまってミスをしたりするなど悪循環に陥ることがあるでしょう。
承認欲求とは?満たし方・なくしたい場合は?【公認心理師監修】
承認欲求は「人に認められたい」「分かってほしい」という思いですね。
この思いが強くなるほど、人に認められなかったときに「誰も分かってくれない」と被害者的な考えになってしまいます。

実際よりも大ごとに捉えてしまうんよね
承認欲求が強すぎる人を相手にするとき、コミュニケーションがとりづらいです。
そのため、人間関係がこじれます。



フェードアウトするわ~
承認欲求が強い人の中で、「承認欲求が強すぎる人」は、分かりやすいと思います。
ここでは、一見分かりづらい「隠れ承認欲求」を持っている人についてお伝えします。
距離感がとりづらい、隠れ承認欲求をもっている人とは
ざっくりと一言でいうと「とても話が長い人」です。
話の長い人が、全員隠れ承認欲求を持っているというわけではありません。
話が長かったり、相手の話をさえぎってまで、自分の話を長々とする人がいます。そういう人は、隠れ承認欲求を持っている人が多いといえます。
見分けるポイントがあります。
話していて「ん?なんかちょっとしんどいかも・・・」というような違和感を感じるかどうか、です。
この感覚、後々大きくなることが多いです。



悪い人じゃないから・・と違和感を無視しがち
仲良くなりすぎるとトラブルにもなりかねないので、最初のちょっとした違和感を信じた方が良いです。
特に相手を優先してしまう人、気をつかいすぎてしまう人、自分の判断軸があやふやな人などが「しんどくなる」相手。それが、この「隠れ承認欲求を持つ人」です。
悪人ではないため、「ちょっとしんどいけど耐えてしまう」ことがしんどいポイントです。
- 強い承認欲求を持っている人に対して⇒「関わりたくない」とハッキリ感じられる
- 隠れ承認欲求を持っている人に対して⇒「モヤるけど悪い人じゃないしな」と耐えられる



ハッキリ意見を言える人にとっては、あまりしんどくならない相手みたい
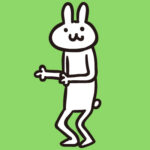
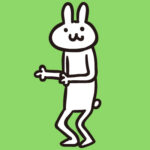
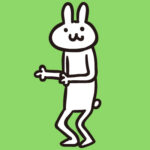
意見を言える人は自分のペースを守れるもんね
やっかいなのが、「誰にとっても、すごくやりづらい人」なわけではないこと。
なので、「しんどい」と感じる人が他の人に相談しても、気持ちを分かってもらえないことがあります。
そこで余計に「自分が我慢すればいいか」「自分のほうがおかしいのかな」と思ってしまい、ストレスが大きくなります。
話の長い人は相手をちゃんと見ていない
話がとても長い、隠れ承認欲求を持っている人。こういう人は自分から相手を見ていません。
どういうことかというと、相手をちゃんと見ている人は、話している途中で相手の反応や表情を気にかけます。
そこから、「話し続けて良いか、やめておくか」判断できます。
隠れ承認欲求を持っている人は、実は「周りからどう見られているか」をとても気にしています。
ダメな自分だと思われたくない。頑張る自分を見てほしい。「分かってほしい」と必死になっているんですね。
そんな思いが強いため、話が長くなります。「すべて話さないと分かってもらえない」という思い込みが強いからです。



聞く方は疲れちゃうよー
例えば親子関係で、親が子どもに対して「あなたのためを思って」と、長々と叱責することがありますね。しかし、その背景には、親自身が「周りに変な親だと思われたくないから、変なことはしないでほしい」という目的があります。
子どもは、「自分のために言ってくれていない」と見抜きます。子どもにとって、話を聞いてもらえない上に、その親の言うことはズレているんですね。
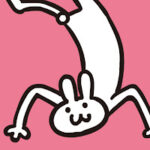
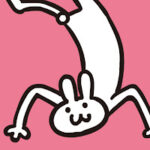
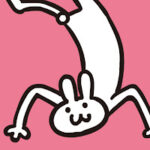
自分のことだけ考えてるんじゃん!ってなるよ
一方的に長々と話をされては、「コミュニケーション」とは言えません。
「周りからどう見られているのか」と気にしすぎるほど、相手を見ておらず、話が長くなります。
近い距離感に自分がイヤと感じたら離れよう


特に、相手のことを優先するクセがある人は、話の長い人の話をつい聞いてあげます。
そして、そのあとにでドッと重たい疲れがきます。この疲れ、蓄積するとキツいんです。



グッタリ疲れるんよね
「しょうがないなぁ聞いてあげるか」というスタンスなら、まだ大丈夫かもしれません。



自分の立場が上司とか、目上だったりね
しかし、「なんかしんどいな」とどこかで感じながらも、黙って聞いてしまいがちな人は気をつけたほうがいいです。
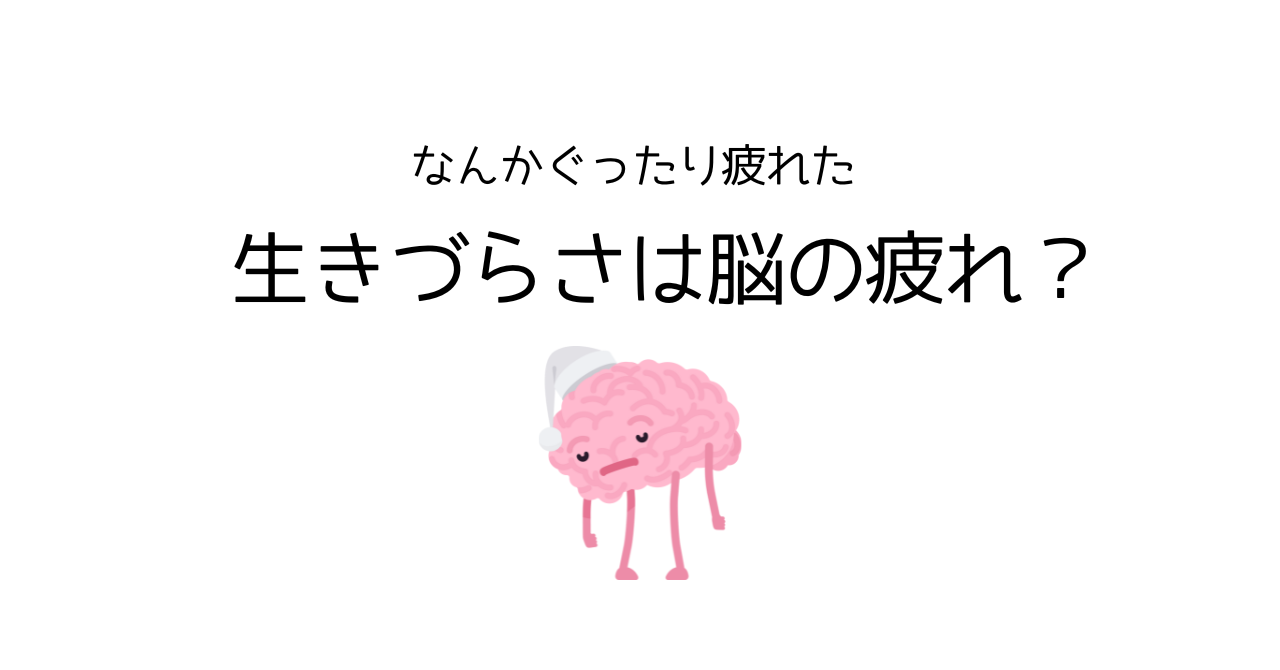
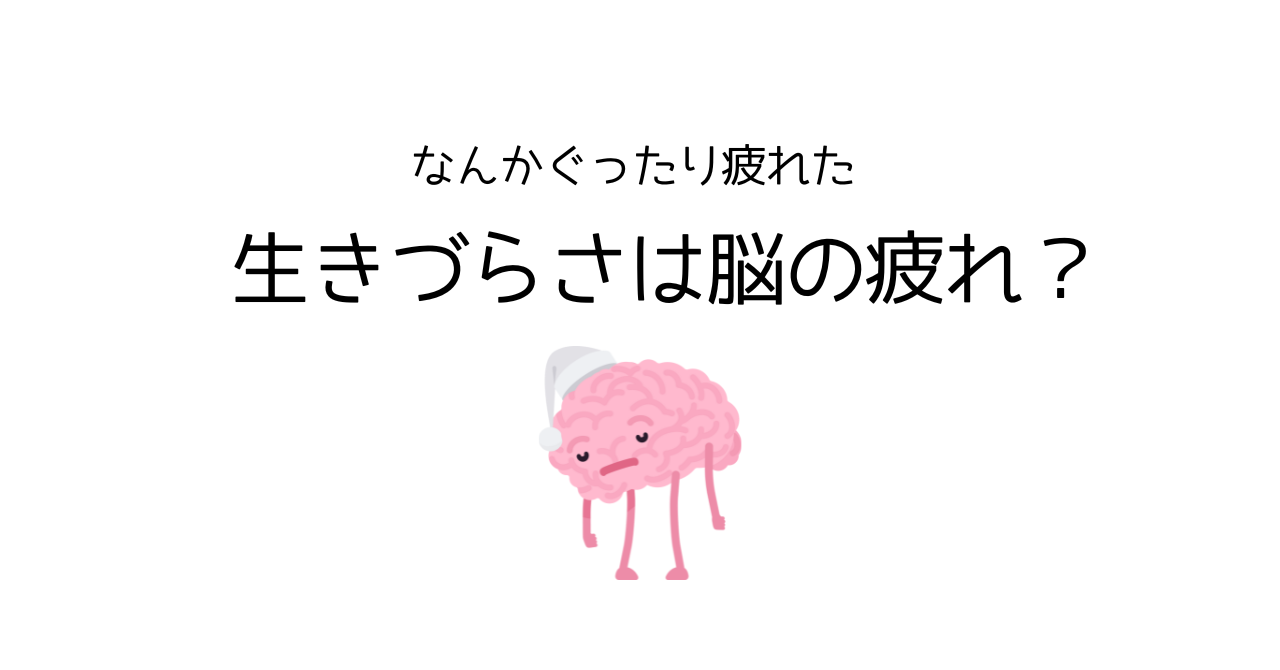
「悪気はない」「他に良いところがあるから」はやめよう
相手を優先してしまいがちな人は、「自分のしんどい気持ち」をいったん横に置いてしまいます。
そして相手を「悪い人」だと思わないようにしてしまうんですね。
人のいいところを見つけることは、素晴らしいことです。でも一番優先してほしいのは「自分の気持ち」です。
相手のことを考えることが、ダメというわけではありません。順番が大事なんです。
まずは自分がどう感じるか。相手が良い人かどうかはそのあとです。
隠れ承認欲求が強い人への対応
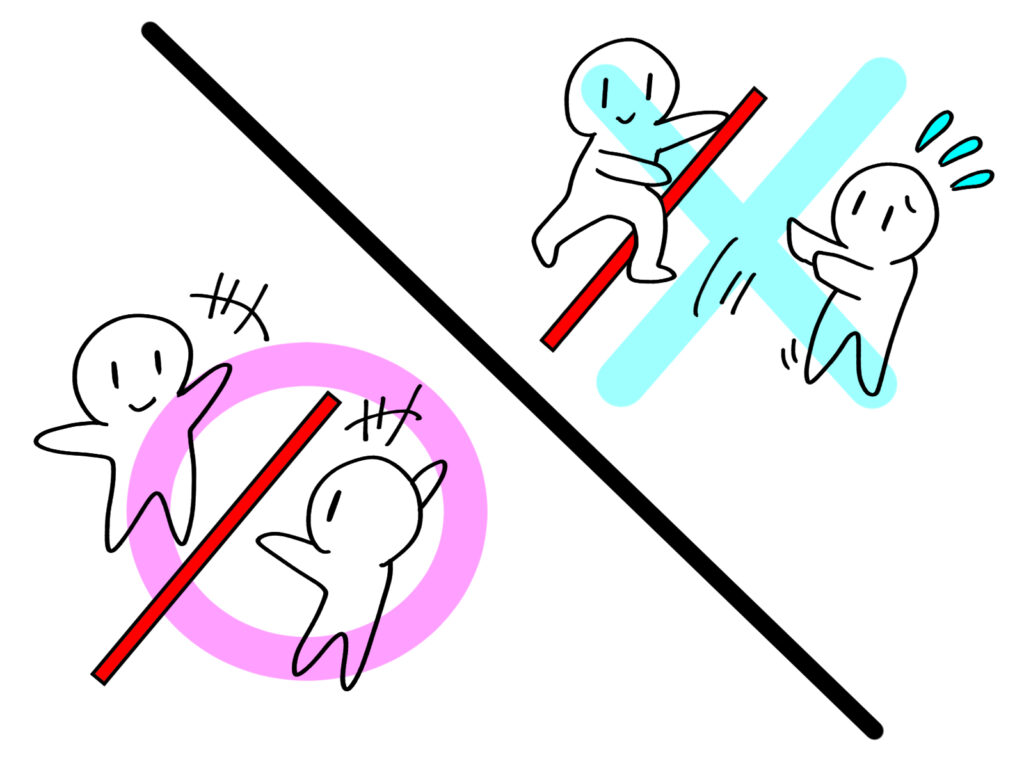
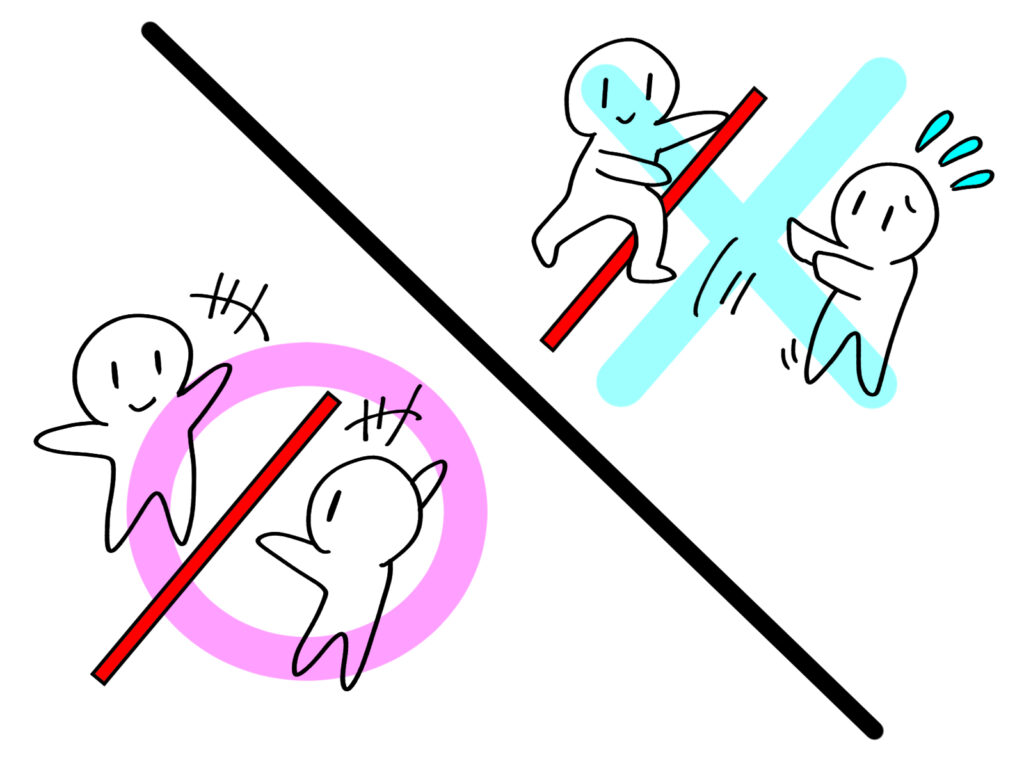
対応は、いくつか自分の中でマニュアルとして持っておくことをおすすめします。
よければこちらを参考にしてください。
- 自分がイヤだと感じたら、距離をおくこと(一時的に、でOK)
- 家族や職場など、どうしても関わる場合は自分から近寄らないこと
- 関わるときは淡々と接すること
- 関わるときは「いい人」にならなくて良い
- できるだけ礼儀正しく接すること
- 笑顔で対応しなくてもいい
- そのコミュニティ内で悪口を言わない(例・職場のAさんのことを同じ職場のBさんに言う)
このような感じで、少しずつ関わらないようにしていると、相手も自然と離れていきます。
ただ、ドライに対応しすぎるのは注意です。「雑に扱われた」と変な恨みを買う可能性があるからです。
隠れ承認欲求を持っている人は、相手の反応に敏感な人が多いです。
特に、被害者意識の強い人には注意。



誰にでも礼儀正しく接していれば問題は起きないよ
仲良くしてたのに急に離れる人
すぐに仲良くなって嬉しかったのも束の間、ある日突然冷たくなった・・・ひどい場合は無視をしてくる始末。
このような距離感が安定しない、距離感の変動がジェットコースターのような人もいます。
私は、中学生のときに体験しました。前日まで仲が良かった子が、突然無視。
例えば、急にラインの既読無視をする人がいます。そんなときは「自分が何かしたのか?」と悶々としてしまいますね。
このような人からは一旦、離れましょう。
やりとりすることすら遮断されるので、自分が何か気に障ることを言ったかどうか、聞くこともできませんよね。
ここで大切なことは「自分がどんな気持ちか」「どうなっていたいか」です。
相手のことを考えても、答えは出ません。



相手のことは相手にしか分からないのよね・・
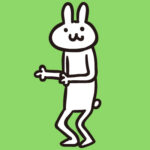
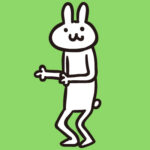
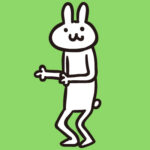
その人は「住処を変える人」というヤドカリのような生き物と思っておく
その人のことではなく、悲しい・寂しい・悔しい・困ったなど、自分の素直な気持ちに焦点をあててみてください。
その気持ちを自分で大切にしてあげましょう。
その人からは離れていいですが、この感じた気持ちを「感じないフリ」をしないように。
感じないフリをすると、ずっとこのモヤモヤを抱え続けることになります。それよりも、しっかり感じた方が、浄化できます。
相手のことを気にしないようにするほど考えてしまうので、相手のことを考えてもいいです。ただ、考える量は自分のことを多めにしてみてください。
ネガティブな気持ちをちゃんと感じてあげると、好きなことや癒されることに集中できます。



好きなもの食べて、好きな音楽聞いて、好きな漫画読もう
自分が好きなものや癒されることに集中できないときは、まだ自分の気持ちを感じきれていないかもしれません。
しっかりと気持ちを感じてあげてください。



クソがーーー!!とか思って良いんよ
紙に書くのもおすすめです。こちらは「自分軸を整える日記の書き方」についてです。お役立てください。
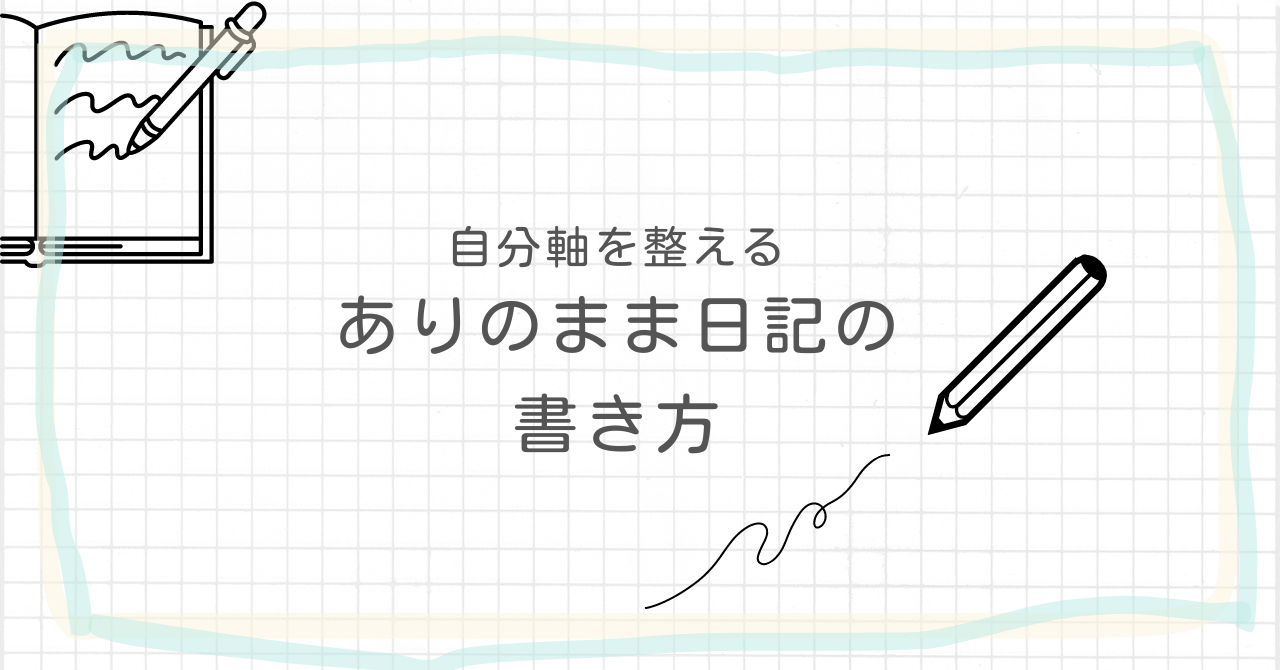
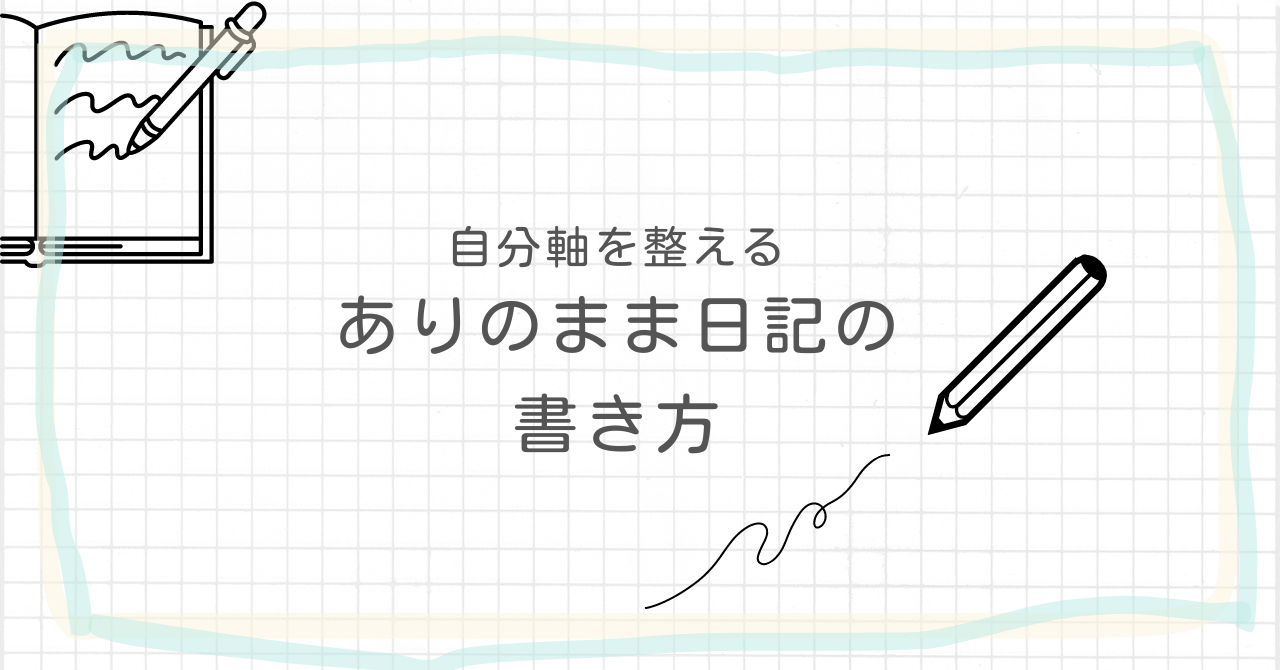
距離感がうまくとれない相手は、その相手自身に問題があります。
運悪く巻き込まれてしまったときは、自分の回復に努めてください。まずは自分を守りましょう。
少なくとも、自分を責めることはありません。
最後に
今回は「急に距離を詰めてくる人」についてお伝えしました。
一方が我慢する関係は「心地良い関係」とはいえませんよね。
そんな人との付き合いをやめると、自分が望む人と出会えたりします。
あなたのまわりに素敵な人が集まりますように。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
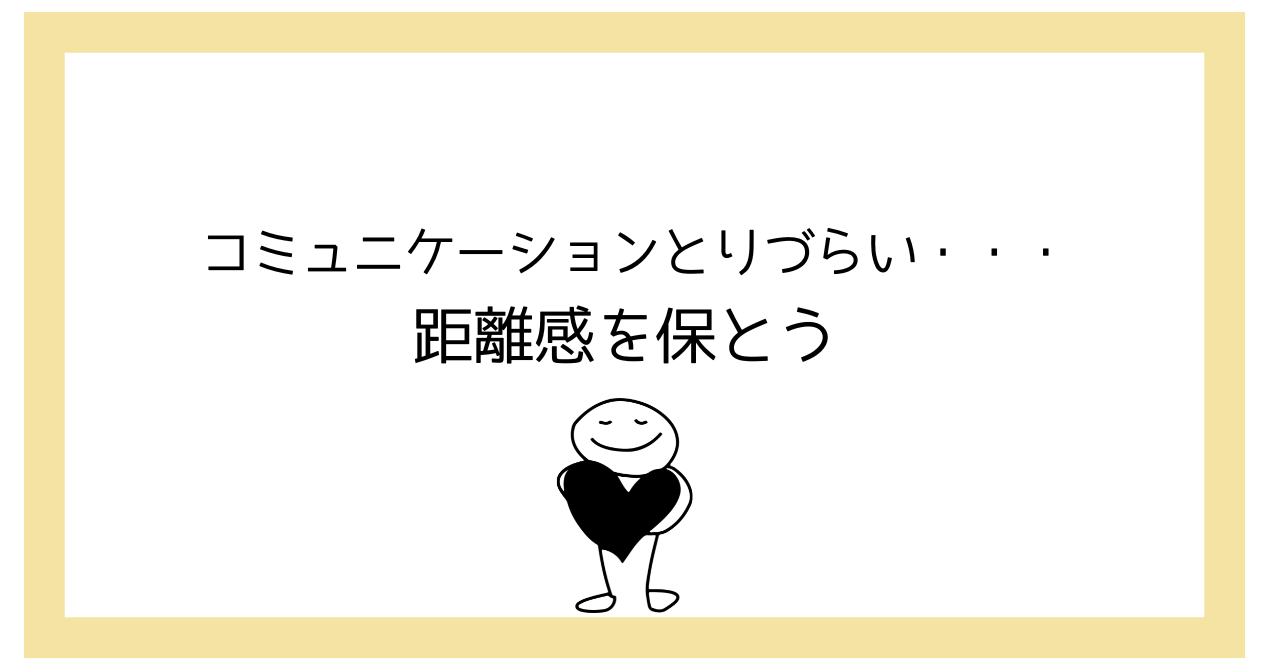
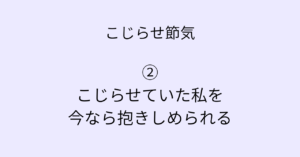
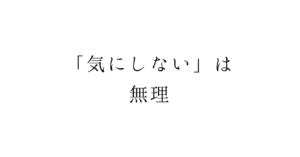
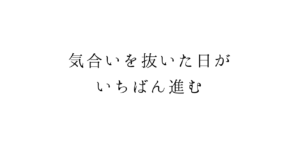
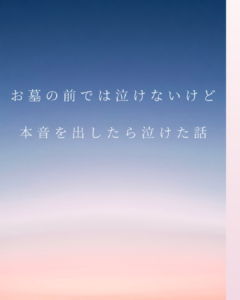
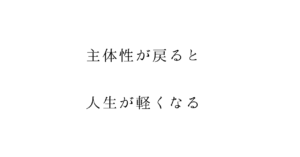

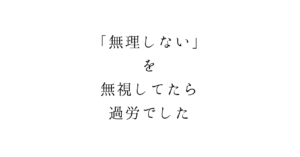
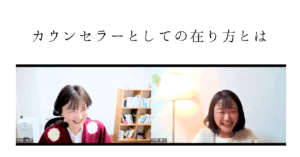
コメント